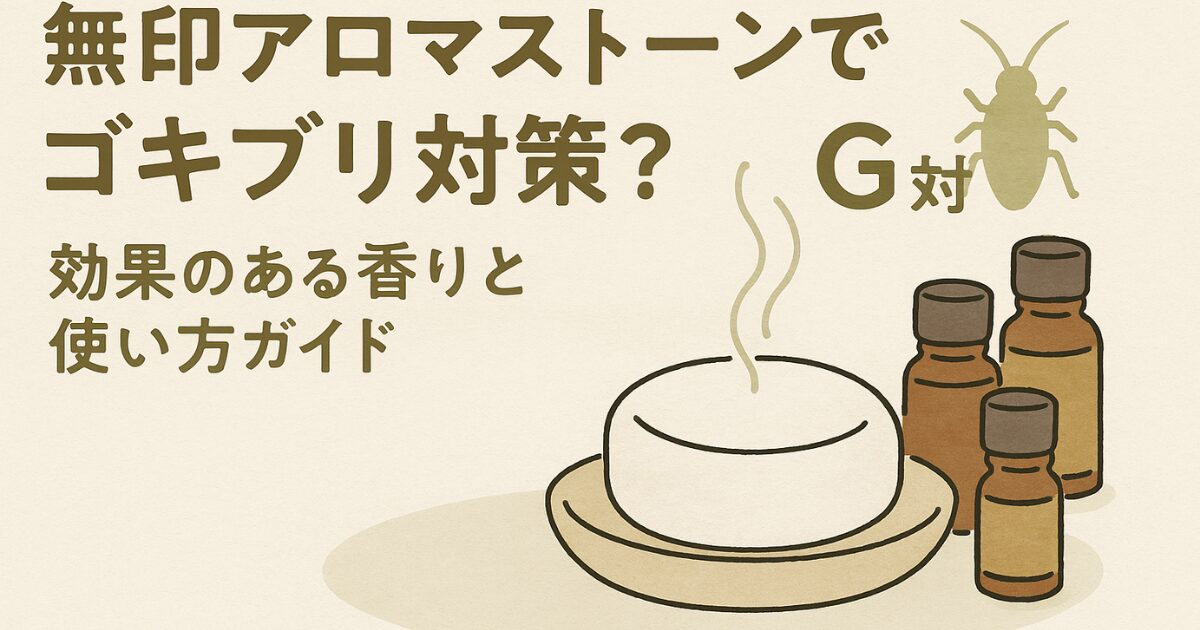こんにちは!satoshiです。
無印良品の「アロマ加湿機」をお探しですか?実は現在、無印良品では加湿機能付きのアロマディフューザーは公式には販売していないんです。えー!もう買えないの?と疑問に思ったそこのあなた!大丈夫!この記事では、過去に販売されていた加湿機能付きモデルの情報や入手方法、そして現行の香り専用ディフューザーラインナップまで徹底解説します。アロマと加湿の両方を楽しみたい方にぴったりの情報になっていますので、最後までしっかり読んでいってください!
無印良品にアロマ加湿機はまだあるの?販売状況を徹底調査

「無印良品ってアロマディフューザーと加湿器が一緒になった商品があったよね?」と思って探している方、残念ながら現在の無印良品では加湿機能付きアロマディフューザーは公式では販売されていません。では現行で発売されているディフューザで水蒸気の出ているやつは?と疑問に思う方もいると思いますが、無印良品の公式サイトでも発表されているように、現行のアロマディフューザーは香りを楽しむための製品であり、加湿機能は搭載されていないんです。
でも、実は過去には「無印良品 超音波アロマディフューザー・大(加湿機能付)」という商品が販売されていました。この製品は人気だったため、現在でもAmazonや楽天、Yahoo!ショッピングなどで在庫限りで販売されているケースがあります。また、メルカリなどのフリマアプリでも時々出品されているのを見かけることがありますよ。
現行の無印良品ディフューザーシリーズは、「コードレス超音波アロマディフューザー」や「水を使わないアロマディフューザー」、シンプルな「アロマストーン」などがラインナップ。これらは香りを楽しむ目的で設計されており、うるおいを加えるタイプでも加湿器として使えるほどの加湿効果はないと公式が言っているので期待しない方がいいでしょう。
次のセクションで、過去に人気だった「無印良品 超音波アロマディフューザー・大(加湿機能付)」はどのようなスペックと魅力があったのかをおさらいしていきたいと思います。
無印良品 超音波アロマディフューザー・大(加湿機能付)の魅力とスペック
「無印良品 超音波アロマディフューザー・大(加湿機能付)」は販売中止された今でも人気商品なんです。この商品がどれほど優れていたのか、詳しくスペックを見ていきましょう!
加湿量約300ml/hの実力!基本スペックと機能を詳しく紹介

このモデルは加湿機能とアロマディフューザーが一体になった香りと加湿を両立した商品になります。特に加湿性能が高く、1時間あたり約300mlもの加湿量もあり、加湿器単体でも十分なスペックがありました。木造和室で5畳、プレハブ洋室だと8畳までカバーできるまさに実力派です。
消費電力は30Wで、1時間あたりの電気代は約0.81円と経済的。最大で約20時間も加湿と香りを楽しめるので、一日中アロマの香りに包まれたい方にはぴったりでした。さらに、エッセンシャルオイルの自動滴下機能や、フタを開けずに上から給水できる設計など、使い勝手を考えた機能が満載でした。
タンク容量2Lで最大6時間連続使用!使い勝手の良さの秘密

このディフューザーの大きな魅力は、たっぷり2Lのタンク容量。強運転モードでも約6時間の連続加湿が可能だったので、夜寝る前にセットすれば、朝まで潤いと香りが続くんですよ。
付属品も充実していて、ACアダプター、お手入れブラシ、移し替え漏斗、移し替えボトルが付いていました。特にお手入れブラシは、長く使う上で衛生面をキープするのに役立つアイテム。細かいところまで配慮された設計だったんです。
どんなお部屋にも合う?サイズ感とデザインのポイント

サイズは約幅23.5×奥行23.5×高さ24cmと、コンパクトながらも存在感のあるサイズ。重さは約2.0kg(ACアダプター含む)で、女性でも持ち運びやすい重量でした。
デザインはさすが無印良品!シンプルで洗練されたホワイトカラーは、どんなインテリアにも馴染みやすく、主張しすぎないけれど存在感のある佇まいが特徴的でした。機能性とデザイン性を兼ね備えた、まさに隠れた名品と言えるでしょう。
現在は公式販売されていませんが、このスペックを見れば、なぜ今でも探している人が多いのか納得ですよね。次のセクションでは、現在の無印良品で販売されているアロマディフューザーについても見ていきたいと思います。
アロマ加湿機を持っていない方必見!無印良品の現行アロマディフューザーはどれがいい?
加湿機能付きアロマディフューザーが手に入らないとわかって少しがっかりしたかもしれませんね。でも現在、無印良品で販売されている現行ディフューザーシリーズも加湿機能はないものの、とても魅力的な商品があるんです。香りを楽しむ目的であれば、十分満足できる製品が揃っていますよ。それでは、一旦加湿機能のことは忘れて、現在販売されている無印良品のアロマディフューザーを見ていきましょう!
無印良品の現行アロマディフューザーラインナップ

現在、無印良品で販売されているアロマディフューザーは主に3種類。シーンや目的に合わせて選べるラインナップになっています。
現行で発売されている無印良品アロマディフューザー
- コードレス超音波アロマディフューザー(MJ-CAD2):価格3,990円(税込)
- 充電式でコードレス使用が可能な超音波式ディフューザー
- 水タンク容量120mlで、満水時から約4時間稼働
- 水を使わないアロマディフューザー(MJ-HBAL1):価格4,990円(税込)
- エッセンシャルオイルを原液のまま空気圧で噴霧するタイプ
- LED調光機能付きで間接照明としても活躍
- 超音波うるおいアロマディフューザー(MJ-UAD1):価格6,990円(税込)
- 広い部屋でも香りを楽しめるたっぷりミストが特長
- 水タンク容量は約350mlで、適用床面積は約12~15畳
- アロマストーン:価格990円(税込)
- 火や電気を使わない、シンプルな素焼きの陶器タイプ
- エッセンシャルオイルを直接染み込ませて使用
大事なポイントは、これらはあくまでアロマを楽しむための製品で、加湿器としての機能は期待できないということ。超音波タイプは水を使用するため多少の潤いはありますが、お部屋を加湿するほどの効果はないと考えておいた方が良いでしょう。
コードレス超音波アロマディフューザーの特徴と使い方

私が特におすすめしたいのが「コードレス超音波アロマディフューザー」です。このモデルは充電式なので、お好きな場所に持ち運んで使えるのが最大の魅力!寝室はもちろん、リビングや書斎など、気分に合わせて場所を選ばず香りを楽しめます。
コードレス超音波アロマディフューザーの特徴
- 充電時間約3時間で、バッテリー駆動時は約2時間使用可能
- 2段階の明るさ調整ができるLEDライト内蔵
- 適用床面積は約6~8畳と、一般的な部屋サイズに対応
- 抗菌カートリッジ付きで衛生的
使い方はとっても簡単!タンクに水を入れて、エッセンシャルオイルを2~3滴垂らすだけ。充電しながら使うこともできるので、長時間使いたいときも安心です。
ただ、加湿器代わりに使うには水タンク容量が120mlとやや少なめ。あくまでアロマを楽しむための製品なので加湿するパワーまで備えてはいません。
水を使わないアロマディフューザーとアロマストーンの魅力

「水を使わないアロマディフューザー」は、エッセンシャルオイルを原液のまま空気圧で噴霧するネブライザー式。水で薄めないので、エッセンシャルオイル本来の香りを存分に楽しめるのが特徴です。香りの適用範囲は約4.5~8畳で、運転モードは強・弱の2段階。
温かみのある電球色のLEDライトは無段階調光式なので、間接照明としても使えます。タイマー機能も付いていて、8時間で自動OFFになるのも便利ですね。
一方、「アロマストーン」は電気を一切使わないシンプルな陶器製のディフューザー。へこんだ部分にエッセンシャルオイルを5~10滴垂らすだけで使えます。デスク周りやベッドサイドなど、小さなスペースで香りを楽しみたい方や、就寝中もアロマを楽しみたい方にぴったり。価格も990円とリーズナブルなのが魅力です。
どの製品も無印良品らしいシンプルで洗練されたデザインなので、インテリアにも馴染みやすくオシャレなものばかりです。次のセクションでは、どうしても加湿とアロマを一緒に楽しみたい方向けの代替案についてご紹介します!
どうしても加湿とアロマを一緒に楽しみたい!代替品と互換アイテムの選び方
「やっぱり加湿とアロマの両方を一緒に楽しみたい!」と諦められない方も多いですよね。無印良品の加湿機能付きアロマディフューザーが手に入らないのは残念ですが、諦めるのはまだ早いです!代わりになる素敵な選択肢をいくつかご紹介します。
他メーカーのアロマ対応加湿器おすすめ3選

現在、多くのメーカーからアロマ対応の加湿器が販売されています。特に超音波式の加湿器は、専用のアロマトレイが付いていることが多いんですよ。以下は加湿機能付きアロマディフューザーを選ぶ際のポイントを書いておきます。
加湿機能付きアロマディフューザーを選ぶときのポイント
- タンク容量2L以上のモデル:長時間使用したい方には、無印良品の旧モデルと同等以上のタンク容量があるものがおすすめ。一晩中稼働させても朝まで持つサイズを選びましょう。
- 静音設計のモデル:寝室で使う場合は特に、動作音の静かなものを選ぶと快適です。多くのメーカーでは30dB以下の静音設計を謳っているものがあります。
- お手入れのしやすさ:加湿器は定期的な清掃が必要です。タンクの口が広く手が入りやすいもの、フィルターが取り外しやすいものなど、お手入れのしやすさも重要なポイントです。
私も以前は無印良品の加湿機能付きディフューザーを探していたのですが、その当時は見つからなかったので他メーカー品を使っていました。(現在は今回紹介しているアロマディフューザーと併用して使っています)スペック的には思った以上に満足できるものが多いので、ぜひチェックしてみてください!
無印エッセンシャルオイルと相性の良い加湿器の選び方

無印良品のエッセンシャルオイルは純度が高く香りが良いので、それをそのまま使いたいという方も多いと思います。そんな方におすすめの加湿器選びのポイントは以下の通りです。
無印良品のエッセンシャルオイルと相性の良い加湿器の選び方
- アロマトレイ付きの超音波式加湿器:水タンクにエッセンシャルオイルを直接入れるとプラスチック部分が劣化することがあります。必ずアロマトレイやアロマ用のスペースが用意されているモデルを選びましょう。
- エッセンシャルオイル対応を明記しているもの:すべての加湿器がエッセンシャルオイルに対応しているわけではありません。必ず「アロマ対応」や「エッセンシャルオイル使用可能」と明記されている製品を選びましょう。
- 拡散力の高いもの:ミストの出力が調節できるモデルや、ミストを広範囲に拡散する機能があるモデルだと、香りも効率よく広がります。
私の経験では、無印良品のエッセンシャルオイルは香りが繊細なので、あまり強力な加湿器だと香りが薄まってしまうことがあります。加湿力と香りのバランスが取れたモデルを選ぶといいですよ。
加湿器とアロマディフューザーを別々に使う方法と利点

実は、加湿器とアロマディフューザーを別々に使うという選択肢もあるんです。これにはいくつかの利点があります。
加湿器とアロマディフューザーを別々で使うメリット
- それぞれの機能を最大限に活かせる:加湿は加湿器に、香りはディフューザーに専念させることで、それぞれの性能を最大限に引き出せます。
- 使い分けが可能:加湿だけしたい時、香りだけを楽しみたい時など、その時の気分や体調に合わせて使い分けられます。
- メンテナンスがしやすい:加湿器は水垢やカビが気になるので定期的な清掃が必要ですが、ディフューザーだけを使う日があれば、その分メンテナンスの頻度を減らせます。
我が家では、リビングと寝室に加湿器と無印良品の水を使わないアロマディフューザーを使っています。リビングは広いので30畳をカバーできる加湿器と香りを楽しみたいリビングテーブルにアロマディフューザーを置いて香りを楽しんでいます。寝室は大きくないので加湿器を使い、水を使わないアロマディフューザーを置いています。(無印の加湿機能付きアロマディフューザーは息子に取れてしまいましたw)機能を別々にすることによって各機能に専念できるため各製品のスペックを最大限に活かすことができるのが最大のメリットです。私は一体型よりこっちの方がいいなと思っています。
次のセクションでは、なんでもいいから無印の加湿機能付きアロマディフューザーが欲しい!中古でも良いから無印良品の加湿機能付きディフューザーを手に入れたいという方のために、フリマサイトなどでの探し方や注意点をご紹介します!
中古でもゲットしたい!超音波アロマディフューザー・大(加湿機能付)の入手方法
「やっぱりどうしても無印良品の加湿機能付きディフューザーが欲しい!」という方、わかりました!ぜひ買ってください!中古品であれば入手できる可能性があります。ここでは、フリマサイトなどで効率的に探す方法をご紹介します。
フリマサイトでチェックすべきポイントと相場価格

メルカリやラクマ、ヤフオクなどのフリマサイトでは、時々「無印良品 超音波アロマディフューザー・大(加湿機能付)」が出品されています。私も定期的にチェックしているのですが、人気商品なのでかなり早く売れてしまうことが多いんです。
相場価格は状態によってかなり差がありますが、だいたい以下のような感じです。
フリマサイトでのだいたいの販売価格
- 未使用・新品同様:元価格と同等か少し高め(希少価値があるため)
- 使用感少なめの美品:8,000円~10,000円程度
- 使用感あり・動作確認済み:5,000円~7,000円程度
私が見ている限りこのくらいの値段が相場。元々は2万円前後で販売されていた商品なので、状態の良い中古品でも比較的お得に手に入ることもあります。ただし、人気商品なので「プレミア価格」がついていることもあるので注意が必要です。
中古品を購入する際の注意点とメンテナンス方法

フリマサイトで購入する際には、以下のポイントをしっかりチェックしましょう。
フリマサイトで購入するときの注意点
- 必ず動作確認済みかどうか確認する:「電源は入るけど、ミストが出ない」などのトラブルが起きることもあります。出品者に動作状況を詳しく聞いておきましょう。
- 付属品の有無をチェック:ACアダプター、お手入れブラシ、移し替え漏斗、移し替えボトルなどが揃っているかを確認。特にACアダプターは必須です。
- 内部の状態や清掃状況を確認:加湿器は水垢やカビが発生しやすいので、できれば内部の写真もリクエストするといいでしょう。
中古品を購入したら、まず徹底的にクリーニングすることをおすすめします。クエン酸水やお酢水を使って内部の水垢を除去し、専用のブラシでタンク内部をきれいにしましょう。特に超音波振動板は性能に直結する部分なので、丁寧に掃除することが大切です。
私も中古で購入した際、最初はミストの出が悪かったのですが、超音波振動板を丁寧に掃除したら見違えるように良くなりました。少し手間はかかりますが、きちんとメンテナンスすれば長く使えますよ。
また、無印公式サイトでも部品であれば売っている商品もあったりするので、もしうまく動かないときや性能が落ちていると感じたら部品を取り寄せて交換することもおすすめします。
出品を見逃さない!通知設定と効率的な探し方

人気商品なので、出品されたらすぐに売れてしまうことが多いです。効率的に探すためには、以下の方法がおすすめです。
効率的に探すためのコツ
- キーワード通知の設定:メルカリやラクマでは「無印 アロマ 加湿」「無印 加湿器」などのキーワードで通知設定をしておくと、新しい出品があったときにすぐに知らせてくれます。
- 複数のキーワードで検索:「無印 アロマディフューザー 大」「無印 加湿 ディフューザー」など、複数のキーワードバリエーションで検索してみましょう。出品者によって商品名の書き方が異なることがあります。
- 定期的なチェック:特に夜8時以降や週末は新しい出品が増える傾向があります。時間帯を見計らってチェックするのも効果的です。
- 複数のプラットフォームをチェック:メルカリだけでなく、ラクマ、ヤフオク、ジモティーなど複数のサイトをチェックすると、見つかる確率が上がります。
私自身はこの方法でよく探していました。根気よく探せば、きっとあなたにもチャンスが訪れますよ!次のセクションでは、無印良品のエッセンシャルオイルを最大限に活かす方法について見ていきましょう。
無印良品のエッセンシャルオイルを最大限に活かす方法
アロマディフューザーを手に入れたら、次は良質なエッセンシャルオイルを選びたいですよね。無印良品のエッセンシャルオイルは、シンプルなパッケージながらも品質が高く、種類も豊富でコスパも良いんです。どんなラインナップがあるのか、使い方のポイントとともにご紹介しますね!
目的別おすすめ!無印良品エッセンシャルオイルシリーズ

無印良品のエッセンシャルオイルは大きく分けて「ブレンドタイプ」と「シングルタイプ」の2種類があります。
ブレンドタイプ(目的別)
- おやすみブレンド:就寝前のリラックスタイムにぴったり
- フローラル:スウィートオレンジ、ゼラニウム、マンダリンなどをブレンドした優しい花の香り
- ウッディ:ラベンダー、スウィートオレンジ、ひのきなどをブレンドした落ち着きのある香り
- ハーバル:スウィートオレンジ、サイプレス、シダーウッドなどの深呼吸したくなる香り
- くつろぎブレンド:リラックスタイムに
- フローラル:ラベンダーをベースにスウィートオレンジなどをブレンドした穏やかな香り
- ウッディ:温州みかん、ひのき、ゆずなど日本らしい和の香り
- ハーバル:温州みかん、ホーウッド、マジョラムなどの心地よい香り
- すっきりブレンド:気分転換やリフレッシュに
- シトラス:レモン、ライム、ユーカリなどの爽やかな香り
- ウッディ:ライム、ティートリー、ペパーミントなどの清潔感のある香り
- ハーバル:ローズマリー、メイチャン、ベルガモットなどの明るい香り
シングルタイプ(代表的なもの)
- ラベンダー:リラックス効果が高く、睡眠の質を高めたい時に
- ペパーミント:すっきりとした香りで集中したい時に
- ユーカリ:クリアな香りで空気をリフレッシュしたい時に
- レモン:爽やかな香りで気分を明るくしたい時に
- ティートリー:クリーンな香りで清潔感を出したい時に
私はシングルタイプを使うことは少なく、基本的にはブレンドタイプを使うことのほうが圧倒的に多いです。ブレンドタイプは目的もしっかりしているのでその目的で使うようにしています。その他には、季節によって香りを変えてみたり、集中したいときはシングルで使ったりと色々な使い方をしています。上記で書いた特徴を参考にしながら自分に合ったオイルを選んで楽しんでくださいね。
シーンに合わせた香りの選び方とブレンドアイデア

無印良品のエッセンシャルオイルは、そのままでももちろん素晴らしいですが、自分でブレンドして楽しむのもおすすめです!いくつかのシーン別におすすめの組み合わせをご紹介します。
朝の目覚めをスッキリさせたいとき
- ユーカリ + レモン(2:1):すっきりとした香りで頭をクリアに
- ペパーミント + オレンジ(1:2):爽やかさと明るさを兼ね備えた香り
仕事や勉強に集中したいとき
- ローズマリー + ペパーミント(2:1):記憶力と集中力をサポート
- レモン + ティートリー(1:1):クリアな思考を促す香り
リラックスしたいとき
- ラベンダー + スウィートオレンジ(2:1):心地よい安らぎをもたらす香り
- ゼラニウム + ベルガモット(1:1):バランスの取れた落ち着きの香り
寝る前にぐっすり眠りたいとき
- ラベンダー + クラリセージ(3:1):深いリラックスと安眠をサポート
- ベルガモット + サイプレス(2:1):心地よい眠りに誘う香り
ブレンドする際のポイントは、まず少量から試してみることです。私も最初は失敗しましたが、少しずつ比率を変えながら自分好みの香りを見つけていきました。これは私がいいと思う配合量なので自身に合った配合量を見つけてくださいね。エッセンシャルオイルは個性が強いので、互いの香りを消し合ってしまうこともありますから、試行錯誤が大切です。
どうしても納得のいく香りがない、好みの香りがない場合はブレンドされているタイプを使うのをおすすめします。
まとめ:あなたにぴったりのアロマと加湿の選択肢

いかがでしたか?無印良品の加湿機能付きアロマディフューザーは現在公式には販売されていませんが、アロマと加湿を楽しむ方法はたくさんあることがわかりましたね。
「無印良品 超音波アロマディフューザー・大(加湿機能付)」は、中古市場でも人気の高い商品です。諦めずに探し続ければ、運良く手に入れられるかもしれません。また、値段は上がってしまいますが、楽天市場やAmazonにも商品がある場合もありますのでそちらもチェックしてみてください。
一方で、現行の無印良品ディフューザーシリーズも、それぞれに魅力があります。コードレスタイプの持ち運びやすさ、水を使わないタイプの香りの純粋さ、シンプルなアロマストーンの使いやすさなど、目的に合わせて選べる多様性が魅力です。
また、他メーカーのアロマ対応加湿器や、加湿器とディフューザーの併用という選択肢も、実用的でおすすめできる方法です。どの選択肢を取るにしても、無印良品の高品質なエッセンシャルオイルは、あなたの毎日に豊かな香りをもたらしてくれるでしょう。
最終的には、あなたのライフスタイルや優先したいポイント(加湿重視か香り重視か)、予算、部屋の広さなどを考慮して選ぶことが大切です。完璧なものを求めるよりも、今手に入るもので工夫して楽しむ姿勢が、充実したアロマライフへの近道かもしれませんね。
香りと潤いに包まれた、心地よい空間づくりを楽しんでくださいね!
最後まで読んでいただきありがとうございました!また次の記事で。
関連記事